令和4(2022)年3月12日(土)~4月17日(日)
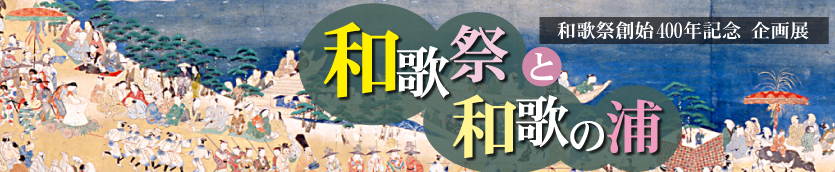
和歌祭は、江戸幕府を開いた徳川家康をまつる紀州東照宮の祭礼です。和歌祭が初めて行われたのは元和8年(1622)のことで、今年で400年の節目の年を迎えます。
和歌山県立博物館では、平成18年(2006)に特別展『和歌祭』を開催し、その後も和歌祭に関係する資料を調査・収集してきました。また、和歌祭に関する研究も進み、平成21年(2009)には和歌祭仮面群 面掛行列所用品が、平成23年(2011)には和歌祭祭礼所用具が、それぞれ和歌山県指定文化財に指定されています。
この企画展では、和歌祭創始400年にあたり、改めて和歌祭や舞台となった和歌の浦を紹介します。
展示のみどころ

① 創設されたころの華やかな和歌祭の様子が描かれています。
東照宮縁起絵巻(とうしょうぐうえんぎえまき) 第五巻(だいごかん)
住吉広通筆(すみよしひろみちひつ) 紀州東照宮蔵
東照大権現(とうしょうだいごんげん)としてまつられた徳川家康の伝記を絵画化したものです。紀伊藩初代藩主徳川頼宣(よりのぶ)が住吉広通に命じて描かせ、東照社(紀州東照宮)に奉納しました。全部で5巻あり、5巻目には東照社の造営と正保(しょうほう)2年(1645)の家康30回忌に行われた和歌祭が描かれています。この絵巻はその翌年に制作されました。
和歌山県指定文化財 〔展示番号1〕

② 江戸時代の終わりに御旅所の位置が変わりました。
紀伊藩の役人が警備のため携帯した絵図と考えられます。
紀州和歌祭礼御道絵図(きしゅうわかさいれいおんみちえず) 個人蔵
東照宮から御旅所までの渡御行列の道筋を中心に、玉津島神社の南から天満宮の鳥居前までの細長い入り江とその周辺が描かれています。嘉永4年(1851)に完成した新御旅所や不老橋も描かれ、御旅所内での建物や関係者の配置を詳しく書いています。藩の役人が警備のために携帯したものではないかとみられます。
〔展示番号12〕

③ 明治時代の和歌祭が描かれています。
なかには、初めて出された練り物もありました。
和歌祭図(わかまつりず) 榎本遊谷筆(えのもとゆうこくひつ) 個人蔵
大正9年4月に行われた和歌祭(藩祖(はんそ)御入国300年祭)が色鮮やかな色彩で描かれています。紀伊藩の家臣で、藩のお抱え絵師である笹川遊原(ささがわゆうげん)に学んだ榎本遊谷が、翌年10月に制作しました。母衣(ほろ)の騎馬武者は、明治時代になって初めて出された練り物です。
〔展示番号31〕
展覧会情報
| 会期 | 令和4(2022)年3月12日(土)~4月17日(日) |
|---|---|
| 開館時間 | 9時30分~17時(入館は16時30分まで) |
| 休館日 | 月曜日(ただし、3月21日は開館し、翌22日は休館) |
| 観覧料 | 一般280円(230円)、大学生170円(140円) ※( )内は20人以上の団体料金。 ※高校生以下・65歳以上・障害者手帳の交付を受けている方(同伴者を含む)は無料。 ※和歌山県内に在学中の外国人留学生は無料。 ※毎月第一日曜日は無料(会期中では4月3日(日)) |
| 主催 | 和歌山県立博物館 |
| 協力 | 紀州東照宮 |

